1588年、豊臣秀吉(とよとみひでよし)が刀狩り(かたながり)を行なう。
刀狩りとは?
豊臣秀吉(とよとみひでよし)によって1588年に実施された、武士以外の者から刀や槍(やり)などの武器を没収(ぼっしゅう)する政策(せいさく)。
刀狩り(かたながり)は、豊臣秀吉(とよとみひでよし)によって1588年に実施された政策(せいさく)で、武士以外の者から刀や槍(やり)などの武器を没収(ぼっしゅう)することを指す。
刀狩り(かたながり)は、農民や僧侶(そうりょ)などが武器を持つことを禁じるものだった。
刀狩り令は、以下の3つの条文から成り立っている。
1.百姓が刀・脇差(わきざし)・弓・槍(やり)・鉄砲(てっぽう)などの武器を所持することを固く禁じる。
2.取り上げた武器は、京都の方広寺(ほうこうじ)の大仏建立(だいぶつこんりゅう)のための釘(くぎ)や鎹(かすがい)に利用されるとされ、これによって百姓は今世だけでなく来世まで安泰(あんたい)であると説得された。
3.百姓は農具(のうぐ)だけを持ち、耕作(こうさく)に専念(せんねん)すれば、末代(まつだい)にわたって無事に過ごせるとされ、これは百姓への配慮(はいりょ)から行なわれたとされている。
刀狩り令(かたながりれい)は、戦国時代における武士と農民の身分的な分離(ぶんり)を強化し、農民が自ら武装(ぶそう)して一揆(いっき)を起こすのを防ぐための法令(ほうれい)だった。この刀狩り(かたながり)によって、武士階級(ぶしかいきゅう)と農民階級(のうみんかいきゅう)の間の明確(めいかく)な区別が生まれ、近世(きんせい)封建体制(ほうけんせいど)の基礎(きそ)が築かれた。
刀狩り(かたながり)はまた、当時全国統一(ぜんこくとういつ)を進めていた秀吉にとって、一揆(一揆)や反乱(はんらん)を抑制(よくせい)するための重要な手段でもあった。刀狩り(かたながり)実施後、一部の例外は認められたが、基本的には百姓から武器が取り上げられた。その結果、日本社会における身分制度(みぶんせいど)がより厳格化(げんかくか)していくことになる。
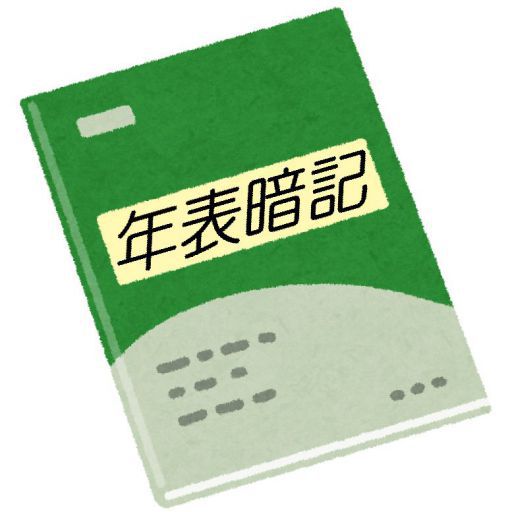


コメント